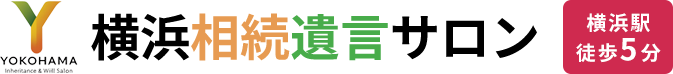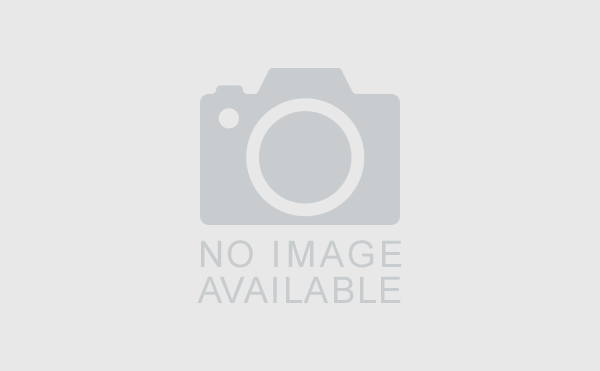公正証書遺言を徹底解説!
「遺言」にはいくつかの方式がありますが、最もおすすめの方式として「公正証書遺言」があります。
公正証書とは、公証人が作成した文書のことです。
公証人とは、主に裁判官や検察官を退職した法律の専門家で、法務局嘱託の公務員の方です。公証人が作成した公正証書は、公文書として、安全性・確実性・有効性が担保されています。
そのため、公正証書遺言は、遺言を作成する場合に最適な方式といえます。
せっかく作成した遺言が無効になってしまうと、相続人全員の合意を前提とした遺産分割協議を行う必要があり、将来に禍根を残しかねませんので、安心・確実である公正証書遺言により行うことを強くおすすめしております。
以下に公正証書遺言についてまとめましたので、参考にしてください。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で証人2人以上の立会いの下に、遺言者が遺言事項を口述して作成する遺言書のことをいいます。
法的に正しい書式で遺言書を作成することができます。
公正証書遺言は、遺言内容を秘密にすることはできませんが、遺言書は公証役場に保管されますので、遺言者の死後、遺言書が発見されないで紛失してしまったり、破棄されたり、その内容が改ざんされたりするおそれはありません。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言には多くのメリットがあります。なるべく公正証書遺言を利用するようにしたいです。
- 法的に最も安全で確実な遺言方式
- 法曹資格者、法曹資格者に準じる学識経験を有する公証人が遺言の作成に関与するため、方式の不備による遺言の無効リスクが極めて低いです。
- 家庭裁判所による遺言書の検認が不要
- 自筆証書遺言や秘密証書遺言では必要な検認手続が不要です。相続開始後、すぐに遺言内容の手続きが可能です。
- 原本の公証役場保管
- 公正証書遺言の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、遺言者が死亡後も確実に内容を確認できます。
- 遺言能力に関する争い可能性減少
- 公正証書遺言作成時に、公証人による本人確認や意思能力を確認を経ますので、後日の遺言無効の主張がされにくくなります。
- 遺言者の自書不要
- 高齢や身体の不自由な遺言者が自書できない場合でも、公証人が遺言者本人に代わり、遺言者の氏名を代書したり、押印することもできます。
- 公証人の出張が可能
- 公正証書遺言は、公証役場以外でも作成することが認められています。
- 例えば、遺言者が高齢や病気等のために公証役場を訪問できない場合、公証人が遺言者の自宅や介護施設、病院等に出張して、遺言公正証書を作成することができます。
公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言にはデメリットもあります。公正証書遺言を利用するにあたり、デメリットも考慮するようにしましょう。
- 費用がかかる
- 財産額に応じた手数料、証人費用、場合によっては、専門家への報酬が別途発生することもあり、費用がかかります。
- 証人2名が必要
- 公正証書遺言作成時に、証人2名の手配が必要で、推定相続人や受遺者はなれないため、第三者に依頼しますが、秘密保持の観点からも心配です。
- 手続きがやや煩雑
- 戸籍謄本等の必要書類の収集、公証役場との事前打ち合わせが必要で、手続きが煩雑です。
- 時間がかかる
- 戸籍謄本等の必要書類の収集にも、公証役場との事前予約・証人の手配など公正証書遺言の作成までに時間がかかります。一般的には1週間から1か月程度かかります。
公正証書遺言作成の流れ
- 推定相続人の調査
- 遺言者は、戸籍謄本の収集など自分の相続人を調べます。
- 相続財産の調査
- 遺言者は、どの財産がどれだけあるか遺漏がないよう調査します。
- 遺言書案の検討・遺留分侵害の確認
- 遺言者は、自己の書き記す遺言内容を検討し、遺言内容により推定相続人の遺留分を侵害していないか確認します。
- 遺言書案の作成
- 遺言者は、遺言書案を作成します。
- 公証人への相談(1回目の公証役場訪問)
- 遺言者は、遺言書案、戸籍謄本、住民票など必要書類を持参のうえ、公証人に相談します。
- 公正証書作成日時予約
- 遺言者は、公正証書遺言を作成する日時を予約します。
- 証人2名の手配
- 遺言者は、公正証書遺言作成時に必要となる証人2名を手配します。
- 公正証書遺言の作成(2回目の公証役場訪問)
- 公証人は、遺言内容を公正証書として作成します。
- 公正証書遺言の正本・謄本の受領
- 遺言者は、公証人から交付される公正証書遺言の正本・謄本を受領します。
公正証書遺言の撤回
公正証書遺言を撤回する場合は基本的に再作成となります。
- 公正証書遺言の全部撤回する場合は、公正証書遺言を全部撤回する旨を新たに作成する遺言書に記載すれば大丈夫です。
- 公正証書遺言の一部を撤回することも可能です。一部撤回をする場合、該当の遺言書のどこの部分を撤回するのか特定したうえで、新たな遺言で改めた内容を明確に記載する方法で行うことができますが、どの部分が変更になったか疑義が残る場合もありますので、一旦全部撤回して、新たに遺言書を作成するのが望ましいです。
公正証書遺言作成の要件
公正証書遺言を有効に作成するためには、以下の要件を満たす必要があります(民法第969条)。
- 証人二人以上の立会いがあること。
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
- 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
- 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
- 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
公正証書遺言作成のために準備するもの
公正証書遺言作成のために準備するものは以下のとおりです。
- 遺言者本人に関するもの
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 印鑑(認印・実印)
- 財産に関する書類
- 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
- 固定資産税評価証明書
- 預貯金の通帳コピー
- 株式・証券等の明細(証券会社の残高報告書など)
- 車両の車検証・保険証など
- その他の資産(美術品・貴金属等)のリスト(評価額付)
- 相続人・受遺者に関する書類
- 相続人全員の戸籍謄本(推定相続人のもの)
- 受遺者の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの
- その他(必要に応じて)
- 遺言の原案メモ(どの財産を誰に遺贈するかなど)
- 証人2名の情報(氏名・住所・職業・生年月日)
公正証書遺言作成の公証役場の手数料
公証役場で必要となる公正証書遺言の手数料は以下のとおり算出します。
①基本手数料(基本部分)
遺言の対象となる財産の価額に応じて、公証人の基本手数料が定められています。
| 目的の価値 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円まで | 5,000円 |
| 200万円まで | 7,000円 |
| 500万円まで | 11,000円 |
| 1,000万円まで | 17,000円 |
| 3,000万円まで | 23,000円 |
| 5,000万円まで | 29,000円 |
| 1億円まで | 43,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算 |
| 3億円を超え10億円以下 | 95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算 |
| 10億円を超える場合 | 249,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算 |
※財産の相続または遺贈を受ける人ごとに上記の表から算出します。
※祭祀主宰者を指定した場合、目的の価額が算定できず、目的の価額が500万円とみなした手数料計算がされますので、11,000円が公証人手数料に加算されます。
②遺言加算
全体の財産が1億円以下のときは、上記の基本手数料に「遺言加算」 として11,000円が加算されます。これは、財産の相続または遺贈を受ける人ごとに加算されるわけではありません。
③原本の枚数による加算
1枚につき250円
※正本・謄本については、1枚からかかり、原本については、3枚を超える場合にかかります。
④正本・謄本の交付手数料
正本・謄本の枚数1枚ごとに250円×枚数
⑤出張して作成した場合の加算等
- 病床執務加算:基本手数料の50%を加算
- 日当:往復に要する時間が4時間までは10,000円、4時間を超過すると20,000を加算
- 交通費:実費
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
公正証書遺言と自筆証書遺言との違いをまとめました。
| 項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成の面倒 | 面倒 | 簡易 |
| 作成方法 | 公証人が口述に基づき作成 | 全文・日付・氏名を自筆で書く(一部例外あり) |
| 作成場所 | 公証役場 | どこでも |
| 費用 | かかる(公証人手数料・証人費用) | かからない |
| 筆記者 | 公証人 | 本人 |
| 証人の有無 | 2人以上の証人が必要 | 不要 |
| 保管方法 | 公証役場が原本を保管 | 自分で保管(法務局に預ける制度もあり) |
| 署名・押印 | 必要(実印)※証人・公証人の署名押印も必要 | 必要(実印、認印でもOK) |
| 秘密性 | 証人が立ち会うためやや低い | 高い(他人に知られにくい) |
| 作成の難易度 | 公証役場への出向・証人依頼など手間がかかる | 比較的簡単 |
| 偽造・紛失リスク | ほとんどない(原本が公証役場に保管) | 高い(紛失・改ざんされる恐れあり) |
| 有効性 | 公証人が確認するため確実に有効 | 内容や形式不備で無効になるリスクあり |
| 封印 | 必要 | 不要 |
| 裁判所の検認 | 不要(すぐに使える) | 必要(法務局保管の場合不要) |