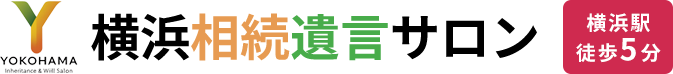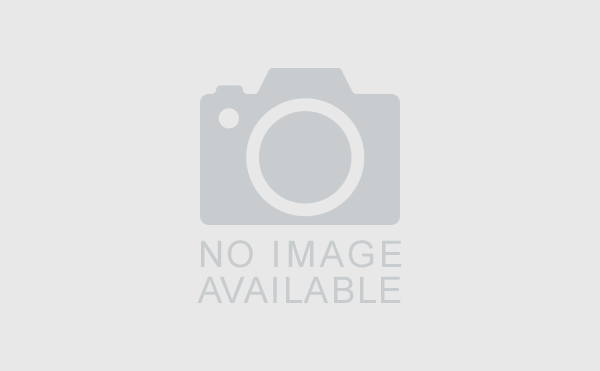相続財産調査を徹底解説!
相続財産調査は、被相続人のプラスやマイナスの財産の全体像を確認・把握するための手続きのことで、相続手続きにおける初期段階の重要なステップとなります。
以下において、相続財産調査について詳細な解説をしております。
相続財産調査とは
相続が発生すると、まず最初に行うべきなのが相続財産調査です。
相続財産調査とは、被相続人(お亡くなりになられた方)の相続財産の有無・内容を調査し、相続財産の範囲(プラス・マイナス、財産の種類や金額)を明確にすることです。非常に重要なステップといえます。
なぜそれほど重要かというと、この調査結果がその後の相続放棄をするかどうかの判断 や遺産分割協議の準備に直接関連してくるからです。
つまり、相続財産調査は「相続手続きのファーストステップ」であり、「相続手続きのすべての判断の土台」となるフェーズといえます。
なぜ相続財産調査が必要になるのか
相続財産調査を行う理由は、主に以下の2点です。
1.遺産分割を行うため
相続人が1人でない(複数人いる)場合、相続人間で、まずは「何を」「誰が」「どれだけ」相続するかを話し合う遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、その前提となる「相続財産の範囲」が不明確なまま協議を開始してしまうと、後になって、「有価証券がまだあった」「借金が残っていた」などの問題が発覚してしまい、遺産分割協議をやり直すことになります。
再度遺産分割協議を行うことは時間も労力もかかり、相続人間の関係を悪化させてしまうこともあります。こういう面倒なことや大きな負担となることを防止するためにも、相続財産調査を最初からしっかりと行う必要があるのです。
2.相続放棄や限定承認を検討するため
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、以下のいずれかを選ぶ必要があります。
・すべてを相続する(単純承認)
・すべてを放棄する(相続放棄)
・プラスの財産の範囲でマイナスの財産も引き継ぐ(限定承認)
この判断を正しく行うためには、被相続人には、「どのような財産」が、「どれほど」あったのかを正確に調査する必要があります。そのため、限られた熟慮期間の中で、迅速かつ正確な調査が求められるのです。
相続財産に含まれるものと含まれないもの
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。一方で、「相続財産に含まれないもの」もあります。
この違いを理解しておくことが、相続手続きの第一歩として、重要です。
1.相続財産に含まれるもの(プラスの財産)
・現金・預貯金:銀行口座、郵便貯金など
・有価証券:株式・公債・投資信託など
・不動産:土地・建物・マンションなど
・動産:自動車、貴金属、骨とう品など
・被相続人が受取人になっている生命保険金
・その他:知的財産権(著作権、特許権など)、ゴルフ会員権、貸金その他の金銭債権など
2.相続財産に含まれるもの(マイナスの財産)
・借入金:金融機関、消費者金融、知人など
・未払金:医療費、家賃、クレジットカード、公共料金など
・他人の債務の連帯保証などの保証債務
3.相続財産に含まれないもの
以下のような財産や権利は 相続財産には含まれません。
・一身専属権:生活保護受給権・年金受給権・雇用契約上の地位など)
・生命保険金・死亡退職金(原則として相続財産には含まれませんが、相続税上はみなし相続財産として扱われます)
・祭祀財産(仏壇・仏具・位牌・お墓などは祭祀承継者が承継します)
金融機関口座の相続手続きの手順
金融機関口座の相続手続きは、以下の手順で進めます。
1.被相続人の金融機関口座を調査
①被相続人の周辺から通帳やキャッシュカードの有無を確認し、どこの金融機関に口座を保有していたか探し出します。
②インターネットバンキングを確認するため、被相続人の電子メール等を確認します。
③取引のありそうな金融機関に口座がないか問い合わせます。
④金融機関から郵送された取引レポート・お知らせ等の書類を確認します。
2.金融機関に死亡したことを通知
金融機関に死亡した旨を電話か訪問して伝えます。これにより、口座が凍結され、預金の入出金や引き落としができなくなります。金融機関から必要書類の案内冊子や解約届を受領します。なお、口座凍結後、無断で口座から引き出すと、以下の問題が生じることがありますので、ご注意ください。
①他の相続人との関係が悪化する可能性があります。
②相続放棄ができなくなる可能性があります。
3.必要書類の準備
戸籍謄本や印鑑証明書等の必要書類を準備します。一般的には以下のとおりです。詳細は各金融機関への確認が必要となります。
① 被相続人の死亡を確認できる書類(戸籍謄本、除籍謄本)
② 相続人代表者が相続人であることを証明できる書類(戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写し)
③ 相続人代表者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内など)と実印
④ 相続人代表者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
⑤ 通帳・キャッシュカード
⑥ 委任状(代理人が相続手続きの申請をする場合)
4.金融機関で口座解約の手続き
口座解約届と必要書類を提出します。残高証明書・利息計算書・取引明細書等の必要な書類の発行の請求を金融機関窓口で依頼します。
5.口座解約・払戻
口座が解約となり、相続人が預金額の払い戻しを受けることになります。
株式の調査方法
株式の調査は以下の手順で進めます。
1.株式の口座を調査
①被相続人の身の回りから、証券会社の取引明細書、年間取引報告書、株主総会や配当・株主優待に関する連絡など金融機関から送付された書類を確認します。
②インターネット証券会社の場合、書類が電子交付されることがあり、郵便物が届かない場合もあります。※電子交付書面をチェックしたいです。
③被相続人が取引をしている可能性のある証券会社に問い合わせを試みます。
④被相続人の株式にかかる口座をどこに開設しているかわからない場合、「株式会社証券保管振替機構(通称「ほふり」)」に対して、必要書類を提出し、所定の手数料を支払のうえ、登録済加入者情報の開示を請求することができます。
不動産の調査方法
2.株式会社証券保管振替機構への開示請求
被相続人の株式にかかる口座をどこに開設しているかわからない場合、「株式会社証券保管振替機構(通称「ほふり」)」に対して、必要書類を提出し、所定の手数料を支払のうえ、登録済加入者情報の開示を請求することができます。
土地、建物、一戸建て、マンションなど不動産の調査方法は以下のとおりです。
●被相続人の不動産の調査
①被相続人の身の回りから、登記済権利証や登記識別情報通知を探索・確認します。
②毎年役所から送付される固定資産税納税通知書・課税明細書を確認します。
共有の場合、代表者にのみ送付されますので、これが送付されず発見できない場合もあります。この場合では、不動産の所在地の市区町村役場において、所有者ごとに土地・家屋の資産状況一覧表である「名寄帳」を取得することができますので、こちらを取り寄せることも大事です。
まとめ:早期の正確な調査が重要です
相続財産調査と聞くと、少し堅苦しい印象を受けるかもしれません。
しかし、実際には、被相続人のお持ちになっていたものを1つ1つ確認して行く作業です。この調査を早めに、正確に行うことで、その後の手続きが驚くほどスムーズになり、思わぬ相続トラブルを未然に防ぐことができます。
行政書士による相続財産調査サポート
被相続人の財産調査、口座・証券・不動産の確認、法定相続情報一覧図の作成まで、一括してサポートいたします。