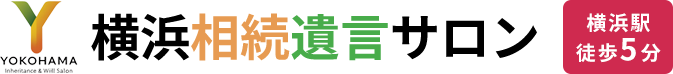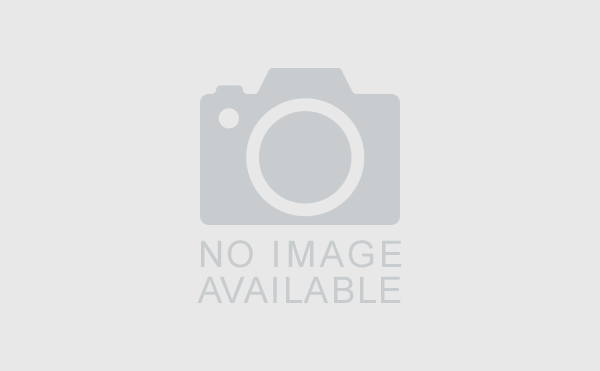相続人調査を徹底解説!
相続人調査は、相続手続きを行うための最初に対応しなければならない非常に重要な手続きです。
しかし、想像以上に、面倒で分かりにくく、また、家族関係や相続関係が複雑な場合は特に難航することもあります。
相続人調査とは
相続人調査とは、被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人が誰になるのか戸籍を収集・確認して調査することです。
金融機関、証券会社、法務局、税務署等への相続の手続きにおいて、相続人が誰になるのか客観的に証明するためには戸籍を揃えて提示する必要があります。
具体的には、被相続人(お亡くなりになられた方)が出生時から死亡時までの戸籍や相続人の戸籍を集めては読み解いていき、必要な戸籍をすべて揃えます。
相続人調査が必要になる理由
1.遺産分割協議は相続人全員で行わなければいけないから
相続が開始しますと、相続財産は相続人全員の共有財産となり、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
もし相続人調査がうまくいかず、相続人が欠けている状態ですと、遺産分割協議は無効になり、遺産分割協議を再度全員で行わなければなりません。そうなってしまうと、余計な手間、時間、労力や費用がかかってしまいます。
遺産分割協議では、協議の内容について相続人全員で合意した遺産分割協議書を作成する必要がありますが、そこには相続人全員の署名・押印が必要となります。相続人調査にて収集・確認した戸籍は、遺産分割協議に記載された相続人が間違いないことを証明する書類となります。
2.想定外の相続人が出てくる可能性があるから
あまり多い訳ではないのですが、相続では、以下のような想定外の相続人が判明することがあるため、そういった相続人の有無を明らかにするためにも、相続人調査は非常に重要となります。
す。
- 被相続人の婚外子
- 相続人の異父母兄弟姉妹
- 被相続人が養子縁組した子
被相続人の身近で生活した相続人の立場ですと、上記の相続人の存在が信じられないということになりますが、もし、そのような相続人がいた場合は、遺産分割協議は全員で行う必要がありますので、上記の相続人と連絡を取り合って、遺産分割を進めていく必要があります。そういった相続人がいなければいないで、その不存在であることを明確にするためにも相続人調査は重要となります。
なぜ相続人調査は困難・大変・面倒なのか
相続人調査は非常に大変で面倒な作業です。理由は次のとおりです。
1.収集・確認すべき戸籍が多いから
収集すべき戸籍の数が多く、通常、1つの役所だけでなく、複数の役所から取り寄せることになります。
自宅から役所が近いといいのですが、遠いことも多いです。郵送の場合ですと、発送や返送用封筒の手配、小為替の封入など、非常に面倒になりますし、時間もかかります。
また、昔の戸籍だと市町村の合併などでどの役所に引き継がれているか分からないことも少なくありません。
なお、2024(令和6)年から導入された「戸籍証明書の広域交付制度」を活用すると、本籍地以外の市区町村でも戸籍が取れるように制度が変更されていますので、従来よりも負担が軽く、戸籍の収集が可能となっております。
2.古い戸籍が手書きであり、解読が難しいから
戸籍には古い戸籍が含まれていることも多く、解読が難しいという点も、相続人調査が大変で面倒である理由のひとつです。
戸籍は、1994(平成6)年以降のものですと、比較的容易に解読できるのですが、古い戸籍は手書きで、しかも旧字体やくずし字を使用して書かれていますので、慣れていないと解読できなくなっているのです。
3.戸籍のつながりがわかりにくいから
収集すべき戸籍の数が多く、通常、1つの役所だけでなく、複数の役所から取り寄せることになります。
自宅から役所が近いといいのですが、遠いことも多いです。郵送の場合ですと、発送や返送用封筒の手配、小為替の封入など、非常に面倒になりますし、時間もかかります。
また、昔の戸籍だと市町村の合併などでどの役所に引き継がれているか分からないことも少なくありません。
なお、2024(令和6)年から導入された「戸籍証明書の広域交付制度」を活用すると、本籍地以外の市区町村でも戸籍が取れるように制度が変更されていますので、従来よりも負担が軽く、戸籍の収集が可能となっております。
戸籍収集が難航することが予想される場合
以下の場合は戸籍収集が面倒になることが想定されます。参考までに収集の必要となる戸籍を記載してみました。
1.被相続人の兄弟が相続人になるケース
被相続人の兄弟が相続人になるケースについては、通常よりも多くの親族関係をさかのぼって確認する必要が生じたり、相続人となる兄弟姉妹ひとりひとりについて、存命か死亡かを確認するための戸籍を収集する必要がありますので、面倒となります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 被相続人の亡父母の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
2.相続人に代襲相続が発生しているケース
本来相続人となるべき方(例えば子や兄弟姉妹)が被相続人の死亡前に死亡しているなどの場合にその子孫の方が代わりに相続人となるもので、相続人の範囲が広がり、相続人の人数が多くなるなど面倒となります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 被代襲者の出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)
- 代襲相続人全員の戸籍(戸籍謄本、戸籍全部事項証明書)
※被相続人の戸籍と重複(共通)する部分は1通の戸籍で兼用できます。
これらにあてはまる場合は収集する必要のある戸籍の通数が多かったり、相続関係が複雑で戸籍の収集が難しくなったりする可能性が高まります。