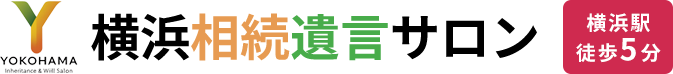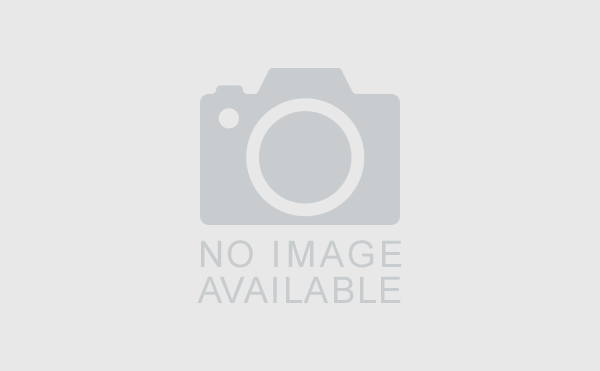遺言書を徹底解説!
遺言書は、自分の死後の相続に関する重要なものですが、多くの方が残していないのが現状です。
理由はさまざまあると思いますが、自分が亡くなっても家族が仲良く遺産を分けるだろうと思っている人が多いことも一因ではないでしょうか。
しかしながら、普通の家族や仲の良かった家族でさえも、意外にもスンナリと行かないのが相続です。
もし遺言がなければ、相続人同士で「遺産分割協議」をする必要があるのですが、これには相続人「全員の合意」が必要です。この「全員の合意」というのがハードルが高いのです。全員が合意できず、紛争となってしまい、弁護士を交えたり、裁判所の判断にゆだねるというケースも多くあります。
遺言があれば、「誰に」「どの財産を」「どれだけ」渡すかを明確にできます。家族同士の紛争を回避できます。
ご自身の財産のせいで、大事な家族が紛争になることのないよう、ご自身の財産をどう渡すかを記載した遺言書を残しておくのは非常に重要となります。
以下において、遺言書について詳細な解説をしております。
遺言書を作成しておいた方がいいケース
被相続人が遺言書を書き残していない場合、法定相続人は全員で遺産分割協議を行い、全員で合意する必要があります。法律で相続の順位や相続分が定められているのですが、なかなか全員の合意というのは難しく争いになるケースも多いです。
特に、以下に該当するケースでは、争いになることも多いですので、遺言書を作成しておいたほうがいいです。
- 特定の相続人により多くの財産を遺したい
- 自身の介護や看病を長年続けてきた相続人に感謝の気持ちとして遺したい場合
- 自身の事業や家業を承継したり、手伝ってくれた相続人に感謝の気持ちとして遺したい場合
- 他の相続人と比べて経済的に困っている相続人を援助するため、より多く残したい場合
- 長い間、音信不通の相続人よりも、頻繁に連絡を取り合っている相続人に親しみを感じるため、より多く遺したい場合
- 内縁の妻(夫)に財産を遺したい
- 法定相続人とはならない内縁の妻(夫)に、遺言書を作成して遺産を確実に遺したいという場合
- 実態は夫婦と変わらない生活をしていますので、感謝や愛情の証として遺産を確実に残したい場合
- 相続人の人数や遺産の種類・数量が多い
- 相続人が多いと、相続人全員の合意が必要な遺産分割協議が難航する可能性が高まりますので、相続人間の争いを予防したい場合
- 遺産が不動産・株式・現金など多岐にわたると、遺産の分け方や評価方法で意見が食い違いやすく、相続人がスムーズに相続手続きを進めることができることを希望する場合
- 特定の相続人に特定の財産を遺したい場合(長男に事業を、二男に不動産を、三男に預金をという場合)
- お子さんがおられず、配偶者に財産を遺したい
- お子さんがいないと、配偶者だけでなく、自身の親または兄弟姉妹が相続人になり、「配偶者」と「自身の親または兄弟姉妹」が遺産分割協議をしなくてすむよう、確実に配偶者だけに遺したい場合
- 相続人以外(息子の妻など)に財産を与えたい
- 相続人以外は、法定相続人でないため、相続権がありませんので、遺言書を作成して遺産を確実に遺したいという場合
- 財産を特定の団体に寄付したい
- 団体には相続権がありませんので、遺言書を作成して遺産を確実に遺したいという場合
遺贈と受遺者
遺贈とは、遺言により財産を贈与することをいいます。
遺言者は、遺贈することによって、お世話になった人、友人など法定相続人以外の人にも渡すことができますし、自分が指定する割合で法定相続人に財産を渡すことができます。
遺贈を行うには、法的に有効な遺言書を作成する必要があります。できるだけ、遺言の効力が無効になる可能性の低い公正証書遺言で行うことをおすすめいたします。
受遺者の種類
遺言によって遺贈を受ける者を受遺者といいます。受遺者は、法定相続人も法定相続人以外も該当します。以下に受遺者の種類をまとめてみました。
| 受遺者の種類 | ポイント |
|---|---|
| 法定相続人 | 配偶者、子ども、親、兄弟姉妹などが該当します。 |
| 法定相続人以外の親族 | 孫、甥・姪、いとこ、叔父・叔母などが該当します。 |
| 内縁の配偶者 | 婚姻と同様の状態にあるものの、婚姻関係にない人が該当します。 |
| 子どもの配偶者 | 介護等でお世話になった人が該当します。 |
| 親しい友人や知人 | 血縁関係がなく、相続権ありませんので、遺言で遺贈することができます。 |
| 法人や団体 | NPO法人、学校、福祉施設などが該当します。 |
包括遺贈と特定遺贈
遺贈には、遺産に対する割合で指定する「包括遺贈」と、特定の財産を指定してする「特定遺贈」とがあります。
| 区分 | 包括遺贈 | 特定遺贈(とくていいぞう) |
|---|---|---|
| 遺贈の内容 | 全部または一定など割合を指定 | 特定の財産を指定 |
| 遺言記載例 | 「全財産の2分の1を●●に遺贈する」 | 「不動産を●●に遺贈する」 |
| 受遺者の権利 | 相続人と同様の権利 | 特定の財産に対する権利 |
| 債務の承継 | 引き継ぐ | 引き継がない |
| 財産目録 | 全体を対象とするため必要な場合あり | 財産特定で済む |
| 放棄 | 家庭裁判所への申述が必要(相続放棄に準じる) | 単に意思表示でOK |
| 不動産取得税 | 非課税 | 課税 |
また、受遺者が遺言者よりも先に亡くなってしまった場合、受遺者に子どもがいても、受け取る権利が消滅します。
受遺者が注意すべきポイント
受遺者が相続人である場合とそうでない場合とに分けて、注意すべきポイントを以下にまとめました。
相続人である受遺者が注意すべきポイント
相続人に遺贈する場合、特別受益(相続人のうちの特定の者が、被相続人から生前または遺言により、他の相続人と比べて特に有利な財産の贈与や遺贈を受けた場合、その利益(受益))として扱われますので、相続分を計算する際に、その遺贈分を一度持ち戻して計算することになります。
例えば、遺贈500万円、他の財産1,000万円の時に、受遺者が500万円+500万円相続するのではなく、遺贈500万円を相続財産1000万円に持ち戻して1,500万円とし、これを2分の1ずつ分けるということです。
相続人以外の受遺者が注意すべきポイント
相続人以外の人に包括遺贈をした場合、包括遺贈を受けた人(包括受遺者)は、財産に対して、相続人とほとんど同じ義務を持つことになります。
①プラスの財産のみでなく、借金(債務)などのマイナスの財産も指定された割合で引き継ぐこととなります。
②相続放棄と同じように手続きをする必要があります。
③相続人全員による財産の遺産分割協議に加わることができますが、相続人との間で協議が必要になり、互いに知らない人同士なので、手続きが難航するケースが多いです。
遺言と遺留分
遺贈は、遺言者が自由に相続人以外にも遺贈をする場合、他の相続人の遺留分を侵害しないようにする必要があります。遺留分を侵害してしまった場合、他の相続人から遺留分侵害額請求されることが考えられます。
遺留分とは?
遺留分とは、 相続財産のうち、一定の相続人に法律上保障された最低限の相続できる取り分のことです。
被相続人がどんな遺言書を作成したとしても、一定の相続人はその相続分を請求する権利があるということになります。
例えば夫妻に子供2人の家庭があったとします。今回、夫が死亡し、相続手続きをすることになりました。
あれこれ、相続財産の調査をしていたところ、夫の遺言書が発見されました。
内容を確認したところ、すべての財産を愛人に渡しますと書き残してありました。
家族の立場からすると、すべての財産が愛人にわたってしまうとなると、これから生活できなくなってしまいます。
そんなことがあっても、家族に対して、最低限の取り分をあらかじめ定めているのが遺留分ということになります。
遺留分の割合
遺留分の割合は、誰が相続人になるのかによって異なります。
- 配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母)が相続人の場合:法定相続分の1/2
例)配偶者と子2人が相続人の場合:
法定相続分は、配偶者が1/2、子がそれぞれ1/4、1/4となります。
遺留分は、上記の割合(1/2)を乗じて算出すると、 配偶者が1/4、子がそれぞれ1/8、1/8となります。 - 直系尊属のみが相続人の場合:法定相続分の1/3
例)父母が2人相続人の場合:
法定相続分は、父母それぞれ1/2ずつとなります。
遺留分は、上記の割合(1/3)を乗じて算出すると、父母それぞれ1/6ずつとなります。
特別受益
「特別受益」とは、被相続人(亡くなった方)から生前に受けた特別な贈与の特別な利益を受けることをいいます。
相続人が生前に受けた特別受益を相続財産に加算し、相続分を再計算することで、他の相続人との間の不公平を是正するための制度といえます。
特別受益に該当するもの
特別受益に該当するものは以下のとおりです(民法第903条)。
- 遺贈
被相続人が遺言により特定の相続人に財産を贈与する行為です。 - 婚姻のための贈与
結婚の際に親から贈与された金銭や財産を指すもので、いわゆる結婚準備金のことです。ただし、金銭や財産が少額であれば扶養の範囲内とみなされ、特別受益と認められないい場合もあります。 - 養子縁組のための贈与
養子縁組の際に養親または実親から贈与された金銭や財産を指すもので、いわゆる支度金のことです。 - 生計の資本としての贈与(独立開業資金や住宅資金の援助など)
生活を維持するための基礎となる財産を贈与することです。具体的には、住宅購入資金、事業資金、不動産などの贈与が挙げられます。
特別受益の持ち戻し
特別受益の「持ち戻し」とは、被相続人が生前に相続人に対して行った贈与や遺贈の価額を相続財産の前渡しとみなし、相続財産に加算したうえで特別受益者の相続分から差し引くことで、相続人間の公平を図る制度です。
・特別受益の計算方法(持ち戻し計算)
特別受益がある場合、以下の手順で相続分を計算します。
①みなし相続財産の算定:相続財産に特別受益額を加算します。
②一応の相続分の算定:法定相続分に基づき、みなし相続財産を分割します。
③特別受益額の控除:一応の相続分から特別受益額を差し引きます。
遺贈をする場合、他の相続人の遺留分を侵害しないようにする必要があります。遺留分を侵害してしまった場合、他の相続人から遺留分侵害額請求されることが考えられます。
・特別受益の持ち戻しの例
相続財産:5,000万円
特別受益:長男に2,500万円の生前贈与
相続人:長男、次男、三男
①特別受益額を相続財産に加算すると、5、000万円+2、500万円=7、500万円となります。
②7、500万円を3人で均等に分けると、1人あたり2、500万円となります。
③特別受益を受けた長男の取り分から2、500万円を差し引くと、長男の取り分は0円となり、次男と三男がそれぞれ2、500万円ずつ受け取ることになります。
特別受益の持ち戻しの免除
特別受益の持ち戻しが行われますと、被相続人が特定の相続人に対して、せっかく生前贈与を行ったことが無駄になってしまい、被相続人の意思を尊重した相続であるとは言えなくなってしまいます。
そのため、被相続人が特定の相続人に財産を渡したい場合、特別受益の持ち戻し免除を行い、過去の生前贈与を考慮せず遺産分割を行うように相続人に指示する必要があります。
特別受益の持ち戻し免除を行う場合、遺言書に「生前に贈与した財産については、持ち戻しを免除する」旨明記することが最も確実でトラブルが起きにくいといえます。
・持ち戻し免除が推定される要件(民法903条の2)
①贈与または遺贈の対象が、居住の用に供する建物またはその敷地であること
②その受贈者が配偶者であること
③婚姻期間が20年以上であること
★民法第903条の2第4項
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。